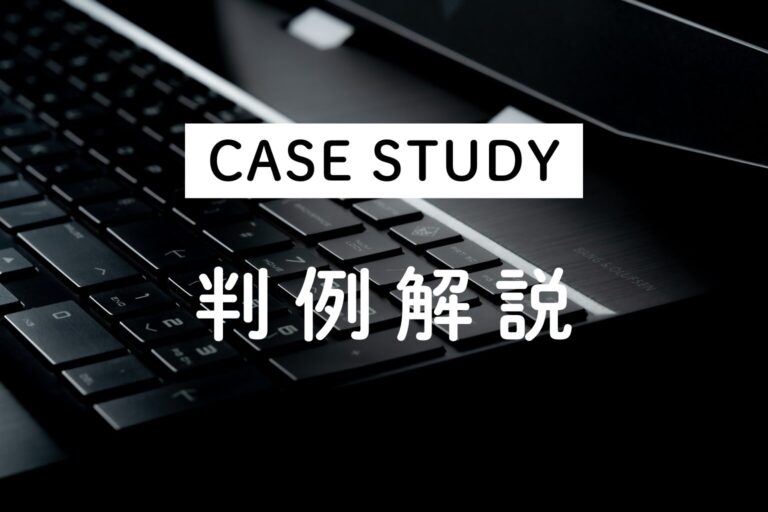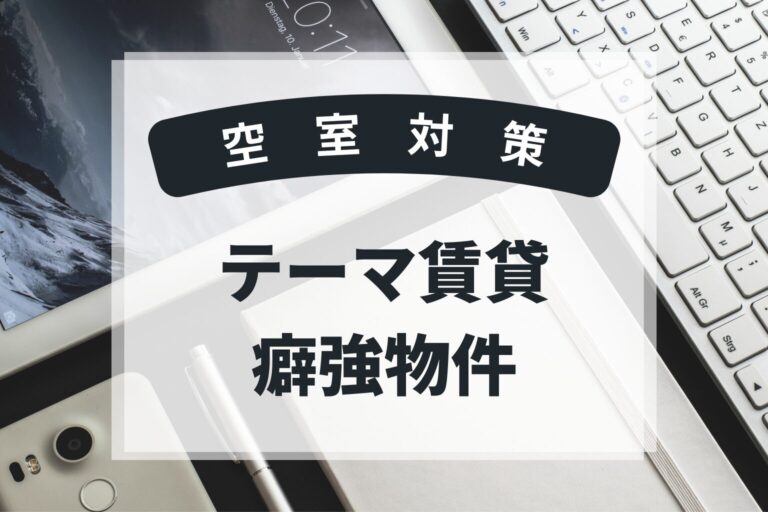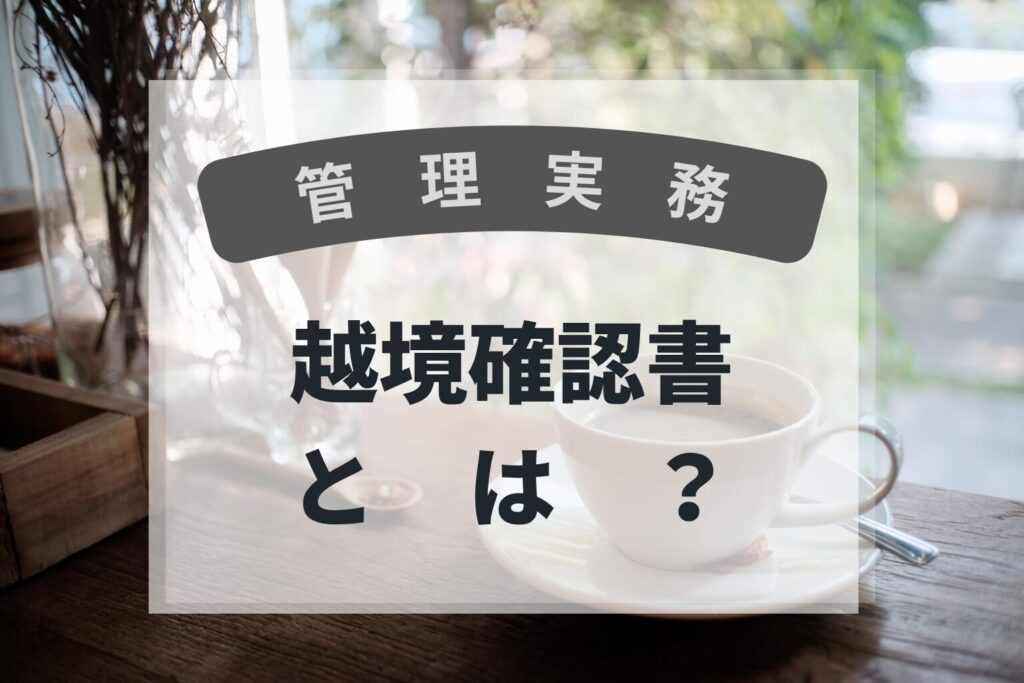
不動産の売買では、隣地との境界をめぐるトラブルを防ぐために「越境確認書」を取り交わすことがあります。この記事では、越境確認書の意味や目的、実務上のポイント、実際に使える文例までをわかりやすく解説します。
不動産売買と越境確認書の概要
土地や建物を売買する際、隣地との境界を確認する過程で「塀が少し越えている」「屋根の一部が隣地側に出ている」といった越境が判明することがあります。このような場合に、当事者間で現状を確認し、将来的な取り扱いを明確にするために作成するのが「越境確認書」です。
越境状態を放置したまま売買を進めると、買主や隣地所有者との間でトラブルに発展するおそれがあります。そのため、越境の有無を明らかにし、双方が合意した内容を文書に残すことが実務上の重要なステップとなります。
越境確認書の目的と内容
越境確認書とは
越境確認書とは、塀・建物・樹木などが隣地との境界を越えている、または越えられている場合に、その事実と今後の取り扱いを当事者同士で確認するための書面です。法律上の義務はありませんが、売買や融資の場面では実務上必須の書類といえます。
越境の典型例
| 区分 | 具体例 | 越境者 |
|---|---|---|
| 構造物 | ブロック塀・フェンス・物置 | 土地所有者 |
| 建物 | 屋根・庇・雨どい・外壁 | 建物所有者 |
| 設備 | 給排水管・ガス管・電線 | 設備設置者 |
| 植栽 | 樹木の枝や根 | 樹木所有者 |
主な記載事項
- 当事者の特定:隣接地の所有者氏名・住所を正確に記載
- 越境物の特定:越境している物の種類・位置・範囲
- 合意内容:現状容認・撤去時期・使用料の有無など
- 承継条項:将来所有者が変わっても効力を持たせる旨
- 署名押印:当事者本人の署名と実印が望ましい
実務上の対応と文例
売買における注意点
売主は、測量や現地調査の段階で越境の有無を確認し、隣地所有者に事情を説明したうえで越境確認書を取り付けるのが一般的です。買主への説明が不足している場合、契約不適合責任の対象となるおそれがあります。
金融機関の融資を利用する場合は、担保物件に越境があると評価に影響するため、越境確認書の提出を求められることがあります。
越境確認書のサンプル文例
越境確認書
甲(○○市△△町1番地 所有者 ○○○○)および
乙(○○市△△町2番地 所有者 △△△△)は、
次のとおり越境に関して確認・合意した。
1. 甲所有地に設置されたブロック塀の一部が乙所有地に約10cm越境している。
2. 乙は本越境について現状のまま存続することを承諾する。
3. 将来、塀を改修・建替えする際は、甲は越境しないよう是正する。
4. 本確認書の効力は、甲乙双方の承継人にも及ぶものとする。
令和○年○月○日
甲:住所・氏名・押印
乙:住所・氏名・押印
確認書の運用ポイント
- 越境が判明した時点で速やかに隣地所有者と協議する
- 書面は2通作成し、双方が保管する
- 現地測量図・写真を添付しておくと、将来の証拠として有効
- 所有者本人の署名を必須とし、代理署名は避ける
まとめ
越境確認書は、不動産売買時に境界をめぐるトラブルを防ぐための重要な書面です。現地での測量・確認を行い、越境の有無を明らかにしたうえで、隣地所有者と合意した内容を明文化することが、安心・安全な取引につながります。特に売主・買主双方の理解と合意形成が、後々の紛争防止に大きく寄与します。
用語解説
- 越境
- 建物や構造物、樹木などが隣地の境界線を越えて設置・生育している状態。
- 境界確定測量
- 土地の正確な境界を明確にするために行う測量作業。隣地所有者の立会いが必要。
- 契約不適合責任
- 売却した不動産に欠陥や説明不足がある場合、売主が買主に対して負う法的責任。