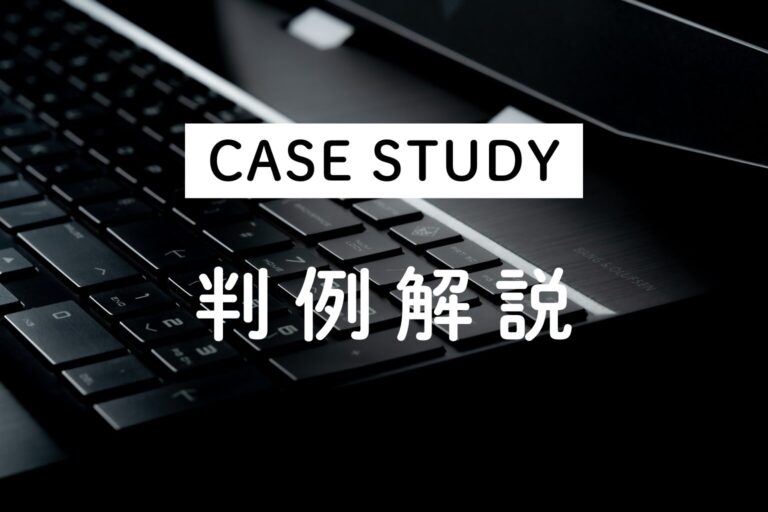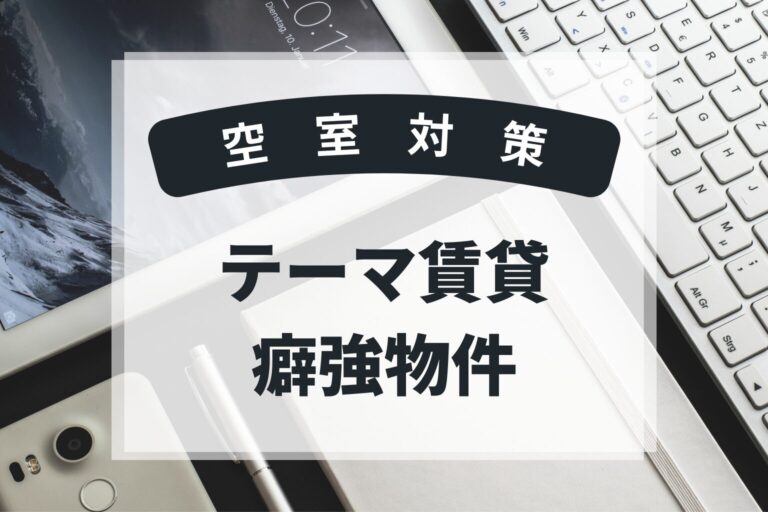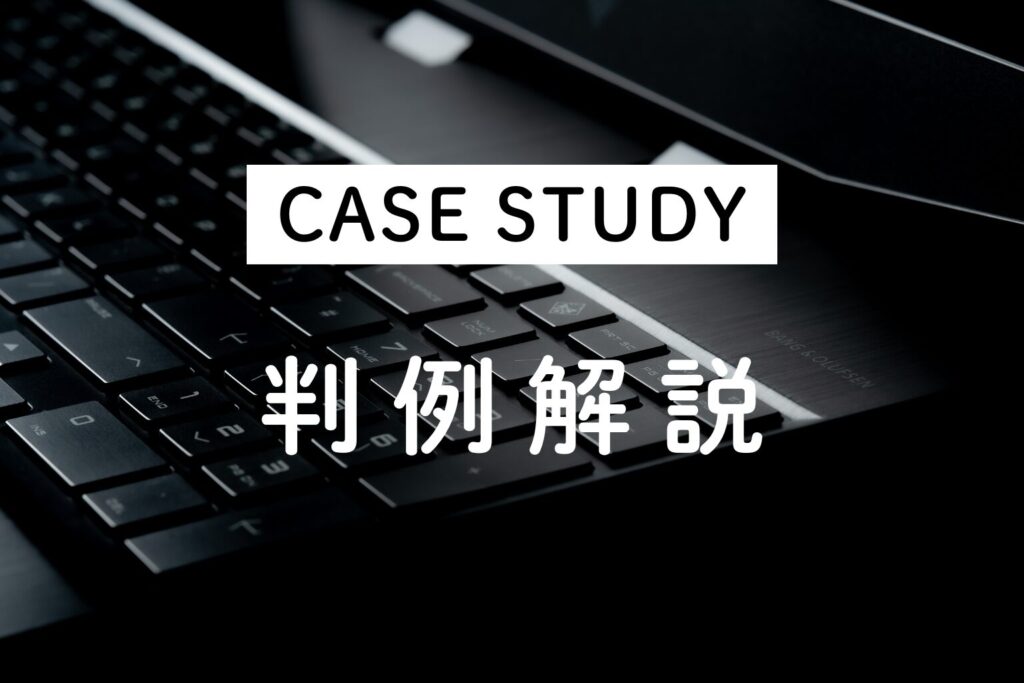
本件は、入居者の迷惑行為(大音量・ごみ放置・近隣への暴言など)を理由に、貸主が賃貸借契約の解除を通知した事案です。裁判所は、信頼関係破壊の程度、注意・是正勧告の有無、違反行為の継続性などを具体的に検討し、契約解除の有効性を判断しました。近年増加する近隣トラブル型の紛争において、実務上の判断基準を示す重要な判例です。
事案の概要
入居者(被告)は、夜間に大音量で音楽を流し、近隣住民から多数の苦情が寄せられていました。また、共用廊下へのごみ放置や暴言・威嚇的態度などの迷惑行為が継続して確認され、管理会社が複数回にわたり注意書面を交付しました。
改善が見られなかったため、貸主は「信頼関係が破壊された」として契約解除を通知し、明渡しを求めました。入居者は「生活音の範囲内であり、契約解除は不当」として争いました。
判決の要旨
- 信頼関係破壊の判断基準:単なる迷惑行為の存在ではなく、行為の態様・回数・悪質性・是正勧告後の態度などを総合的に考慮し、賃貸借契約の信頼関係が回復不能かを判断する。
- 是正勧告・注意喚起:管理会社が複数回にわたって文書・訪問による注意を行ったにもかかわらず、改善が見られなかったことを重視。
- 社会的相当性:迷惑行為が近隣居住者の生活環境を著しく損ね、社会的に許容される範囲を超えていたと認定。
- 結論:信頼関係の破壊が明らかであるとして契約解除を有効と判断し、貸主の明渡請求を認容。
位置づけと実務上のポイント
1. 信頼関係破壊理論の適用
賃貸借契約の解除には、単なる違反行為だけでなく、貸主と借主の信頼関係が社会通念上回復不能に損なわれたかが要件となります。本判決は、繰り返しの迷惑行為と是正拒否がその基準を満たすと判断しました。
2. 管理会社・貸主の対応指針
- 苦情発生時には、日時・内容・対応経過を記録する。
- 注意書面・改善勧告を段階的かつ書面で実施し、履歴を残す。
- 改善が見られない場合には、弁護士・専門機関への相談を早期に行う。
- 退去請求に至る前に、警告・協議・調停などのプロセスを経ることで、解除の合理性を補強できる。
3. 近年の傾向と応用範囲
本件のような迷惑行為型紛争は、騒音・ごみ・臭気・暴言・ペット飼育違反など多様化しています。
裁判所は、「改善勧告を無視した継続的・悪質な行為」を中心に契約解除を認める傾向にあり、管理会社の対応記録が極めて重要です。
まとめ
大阪地判平成29年11月21日判決は、迷惑行為が繰り返され、是正勧告にも応じない場合には信頼関係が破壊されると判断した重要事例です。
管理会社・貸主は、適正な注意・勧告・記録を経て手続を踏むことで、契約解除の適法性を担保できます。日常管理の段階で記録を残す運用が、後の法的対応を左右します。
用語紹介
- 信頼関係破壊理論
- 賃貸借契約の解除が有効となるのは、貸主・借主間の信頼関係が社会通念上回復不能に破壊された場合に限られるとする理論。
- 是正勧告
- 違反行為を改めるよう求める公式な通知。複数回行うことで解除の合理性を補強できる。
- 迷惑行為
- 他の入居者や近隣住民の平穏な生活を妨げる行為。騒音・悪臭・ごみ放置・暴言などが典型例。
- 明渡請求
- 契約解除後に借主に対して建物の明渡しを求める法的請求。信頼関係破壊が要件となる。