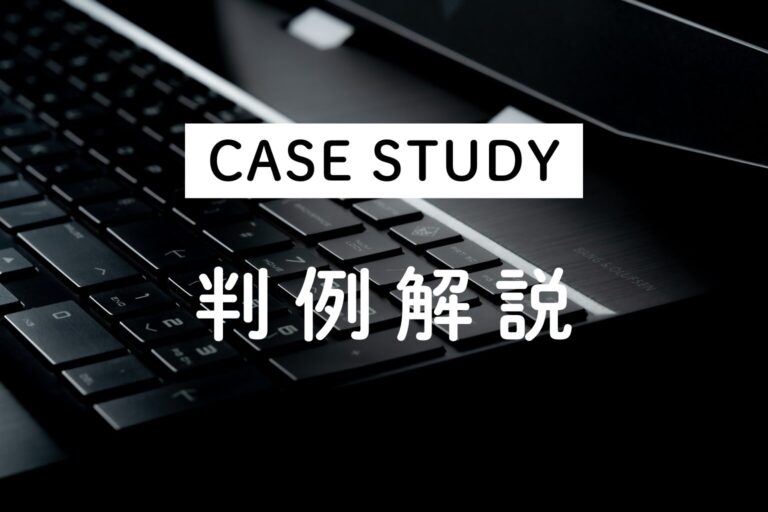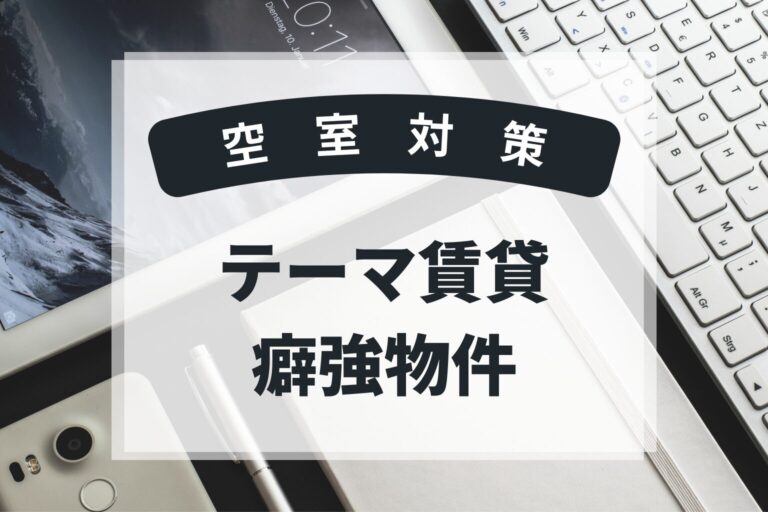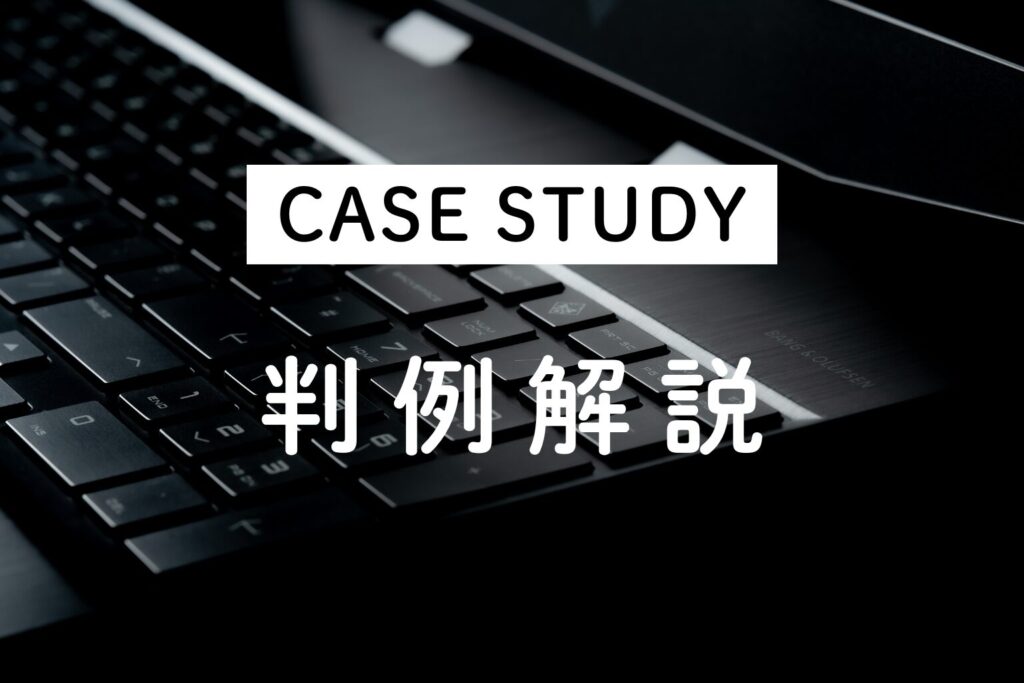
本件は、借主が退去後に生じた原状回復費用や未払賃料をめぐり、連帯保証人がどこまで責任を負うのかが争われた事案です。裁判所は、連帯保証の範囲は賃貸借契約に基づく債務に限定されるとし、契約終了後に新たに発生した費用の一部については保証の対象外と判断しました。本判決は、2017年民法改正における「極度額設定」の考え方にも通じる重要な基礎理論を示しています。
事案の概要
借主が賃貸住宅を退去した後、貸主は未払賃料のほか、室内補修や清掃などの原状回復費用を請求しました。借主が支払いを行わなかったため、貸主は連帯保証人に対しても同様の金額を請求しました。
連帯保証人は「契約終了後に発生した費用は保証の範囲外である」と主張し、保証債務の範囲が争点となりました。
判決の要旨
- 連帯保証債務の範囲:保証人が負うのは、主債務である賃貸借契約に基づいて発生した債務に限られる。
- 契約終了後の債務:契約終了後に新たに発生する原状回復費用等は、契約関係が消滅した後に生じた義務であり、保証の対象外とされる。
- 保証契約の明確性:保証人の責任範囲を明確にするため、契約書に具体的な債務の内容を特定して記載することが必要。
- 結論:本件では、未払賃料についてのみ連帯保証責任を認め、原状回復費用の支払い義務は否定された。
位置づけと実務上のポイント
1. 保証の範囲特定の重要性
本判決は、連帯保証の範囲を「賃貸借契約に基づく債務」に限定する考え方を明確にしました。契約終了後に発生する債務(損害金や遅延損害金、原状回復費など)は、保証契約の文言上明示されていない限り、保証の範囲に含まれないと判断されます。
2. 契約書への明記と極度額の必要性
2017年の民法改正により、個人が保証人となる場合には極度額(上限金額)を定めなければ無効とされました(民法465条の2)。
これにより、保証範囲の明確化が法的義務となり、本判例の趣旨が法制化された形となります。
3. 実務への影響
- 契約書では「保証範囲」「期間」「極度額」を明記し、後の紛争を防ぐ。
- 管理会社は保証会社・個人保証人の契約内容を確認し、保証外債務を誤って請求しないよう注意する。
- 借主・保証人ともに、退去後の費用請求が保証の範囲に含まれるか事前に確認しておくことが重要。
まとめ
東京地判平成27年6月30日判決は、連帯保証人の責任範囲を限定的に解釈し、契約終了後の原状回復費用は保証の対象外と判断した重要な事例です。
本判決の考え方は、2017年の民法改正による極度額設定義務にも通じ、保証契約の透明性・予見可能性を高める基礎となりました。
用語紹介
- 連帯保証人
- 主債務者と同等の責任を負い、貸主から直接請求を受けても拒めない保証人。
- 保証債務の範囲
- 保証人が負担する債務の内容・期間・金額の範囲。契約書で明確に定める必要がある。
- 原状回復費用
- 退去時に建物を適正な状態に戻すための補修・清掃等の費用。契約終了後の費用は保証対象外となる場合が多い。
- 極度額
- 2017年の民法改正で導入された保証債務の上限額。定めがない場合、保証契約は無効となる。