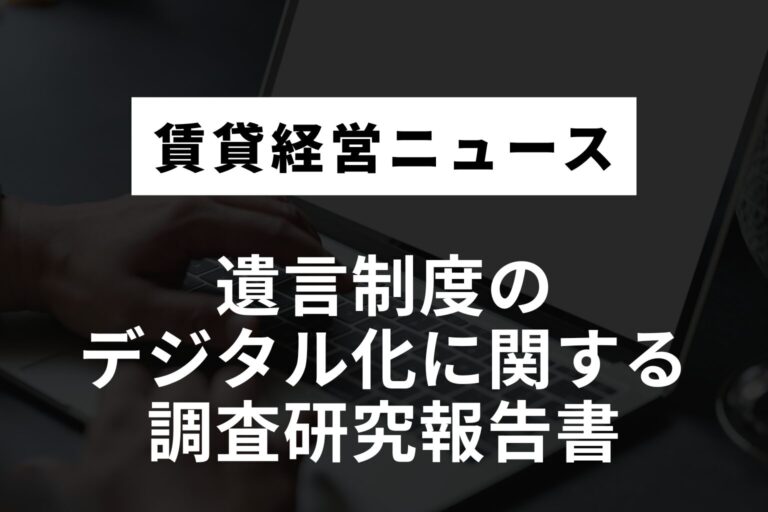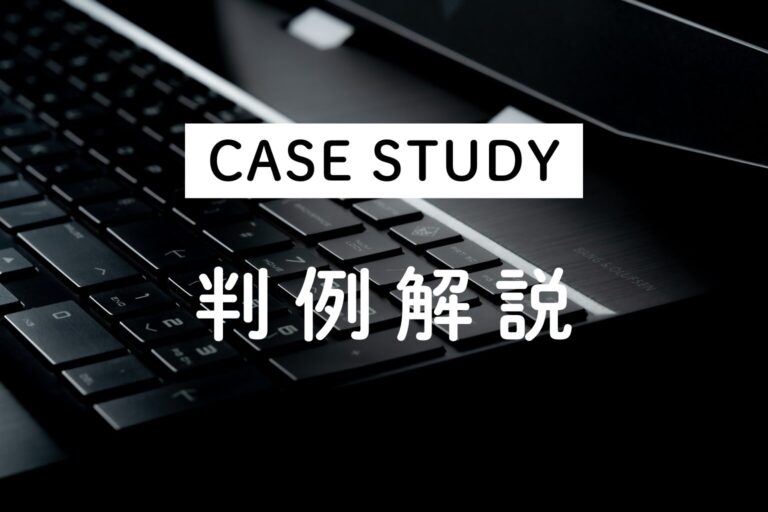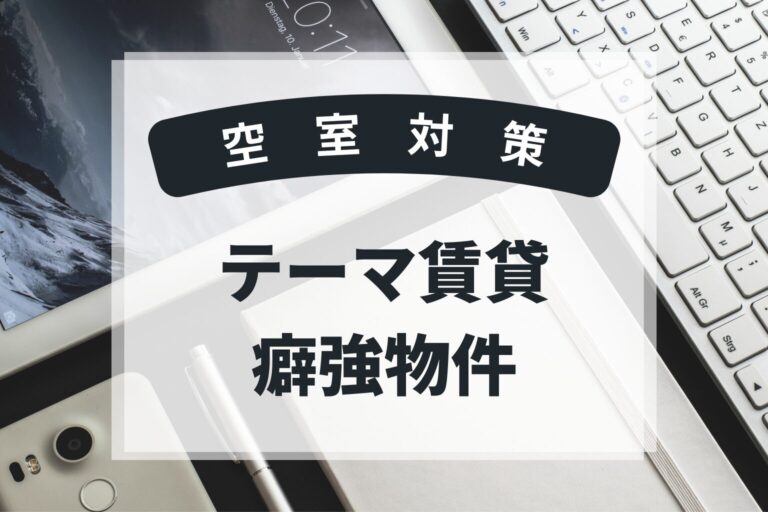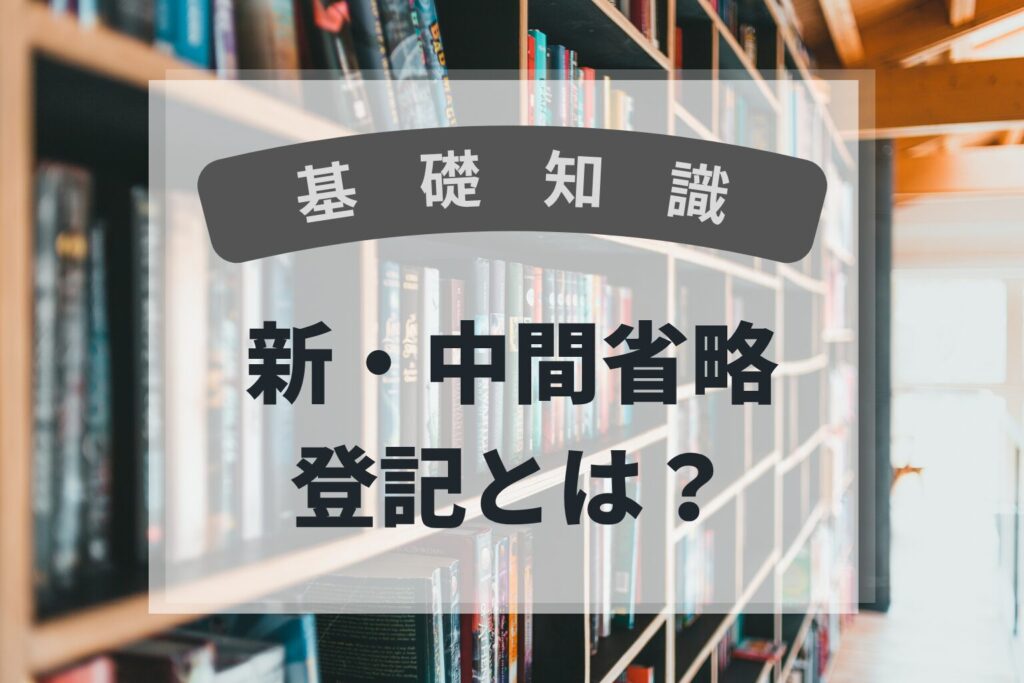
はじめに
不動産取引の世界では、かつて「中間省略登記」という言葉が広く使われていました。AからB、BからCと物件が転売される場面で、中間者Bの登記を省いてAからCへの所有権移転だけを登記する方法です。取引コストの削減にはつながりますが、登記簿の信頼性を揺るがす行為として問題視され、不動産登記法の改正を契機に原則禁止となりました。
一方で、不動産市場の活性化や取引の合理化という観点から、実体としてAからCに直接所有権が移転している場合まで一律に否定すべきかどうかという議論も生まれました。この議論を受けて整理されたのが、いわゆる「新・中間省略登記(直接移転登記)」です。
本記事では、旧来の中間省略登記と新・中間省略登記の違いを押さえながら、制度の背景と法的根拠、具体的なスキームと契約条項の考え方、そして実務上の注意点を整理します。賃貸オーナーや不動産管理会社の担当者が、専門家と会話するときの前提知識として活用できる内容を目指します。
中間省略登記とは
本来の登記の流れと中間省略登記のイメージ
不動産の所有権が移転するとき、登記簿には実際の取引順に権利移転が記録されます。たとえば、Aが土地を所有し、それをBが買い、さらにBからCが買った場合、登記簿上は「A→B→C」と連続して所有権移転が記録されるのが原則です。
これに対して中間省略登記は、AからB、BからCという二つの売買が存在するにもかかわらず、登記の段階だけBを飛ばして「A→C」の所有権移転登記だけを行う方法を指します。中間者Bは実際には売買に関与し、利益も得ますが、登記簿には現れません。
中間省略登記が行われていた理由
中間省略登記が行われていた最大の理由は、コストの削減です。A→B、B→Cと二回の登記を行えば、登録免許税や司法書士報酬などの費用がそれぞれ発生します。これをA→Cの一回にまとめれば、全体の負担を抑えられます。
とくに転売を前提とした取引では、この差が利益にも直結します。そのため、かつては中間省略登記が慣行として用いられた時期がありました。ただし、その利便性の裏側で、制度的なリスクが顕在化していきます。
従来型中間省略登記の問題点
登記簿の公示機能を損なうリスク
不動産登記制度の目的は、権利関係を公に示し、取引の安全を確保することです。本来介在しているはずの中間者Bが登記簿に現れない場合、第三者は実際の取引経緯をたどれません。結果として、権利変動の透明性が失われ、登記簿の信用が下がります。
たとえばBが他方に二重売買を行っていたとしても、登記簿上はその痕跡が残りません。このように、実体と登記が乖離することは、後の紛争の火種になります。
不動産登記法改正と「登記原因証明情報」制度
こうした問題意識から、不動産登記法の改正(平成17年施行)により、登記申請時に「登記原因証明情報」を提供する制度が導入されました。これは、権利変動の原因となった具体的な契約内容や日付を示す情報を提出し、登記と実体を一致させるための仕組みです。
この改正によって、A→B、B→Cという二つの売買契約を経由したにもかかわらず、申請上だけA→Cと記載することは実務上できなくなりました。従来型の中間省略登記は、登記原因証明情報の段階で矛盾が生じるため、制度的に封じ込められた形です。
新・中間省略登記の登場と背景
規制改革と不動産流通の活性化
一方で、土地の有効活用や不動産流通の促進という観点から、取引コストの過度な増加は望ましくありません。そこで、内閣府の規制改革会議は、法務省や国土交通省と協議し、「実体としてAからCに直接所有権が移転している場合」をどのように扱うかを検討しました。
議論の焦点は、「違法な中間省略登記」を認めるかどうかではなく、実体がA→Cの直接移転となっている取引について、登記をどのような法的構成で処理するかにありました。結果として、一定の契約類型に限り、A→Cへの直接移転登記を認める方向で整理が進みます。
「新・中間省略登記」として整理された枠組み
こうした経緯の中で登場したのが、実務で「新・中間省略登記」と呼ばれるスキームです。これは、従来行われていた中間省略登記をそのまま容認するものではなく、
- 契約の構造として、実体が最初からA→Cの直接移転となっていること
- その実体を前提に、登記原因証明情報を整合的に作成できること
を条件として、AからCへの直接移転登記を認めるものです。単なる登記手続の省略ではなく、契約構成と実体に裏付けられた「直接移転登記」として理解する必要があります。
新・中間省略登記の法的根拠
法務省の解釈通知と司法書士向けの整理
新・中間省略登記を支える土台は、まず法務省民事局の解釈通知です。ここでは、実体としてAからCに直接所有権が移転している場合には、「第三者のためにする契約」や「買主の地位の譲渡」を登記原因とするA→Cの移転登記申請を受理する方針が示されています。
この解釈を受けて、日本司法書士会連合会が司法書士会あてに補足通知を発出し、現場の登記実務における判断基準が周知されました。これにより、司法書士は一定の契約類型であれば、AからCへの直接移転登記を前提とした手続設計が可能になりました。
宅建業法施行規則の改正と他人物売買の適用除外
さらに重要なのが、国土交通省による宅地建物取引業法施行規則の改正です。宅建業法33条の2は、宅建業者による「他人物売買」を原則禁止していますが、施行規則の改正により、「第三者のためにする契約」を前提とした一定の取引については、この禁止の適用を除外することが明確化されました。
これにより、宅建業者Bが関与する取引であっても、
- A–B間を第三者のためにする契約とすること
- BC間を他人物売買の形式で締結すること
を条件として、AからCへの直接移転登記を行える余地が生まれました。制度面と実務面の双方で、合法的な直接移転スキームの位置づけが整ったといえます。
新・中間省略登記の代表的スキーム
1. 第三者のためにする契約方式
第一のスキームは、民法上の「第三者のためにする契約」を利用する方式です。AとBが売買契約を結ぶ際、その契約の効果を第三者であるCに帰属させると定めます。Cが受益の意思表示を行うことで、所有権は直接AからCに移転します。
この構成では、Bは契約当事者ではあるものの、不動産の所有権を取得しません。実体としても登記上も「A→C」となる点が特徴です。登記原因証明情報には、第三者のためにする契約の内容とCの受益の意思表示の事実が記載されます。
2. 買主の地位の譲渡方式
第二のスキームは、「買主の地位の譲渡」を使う方法です。まずAとBの間で通常の売買契約を締結し、次にBがその契約上の「買主としての地位」をCに譲渡します。Aがその譲渡を承諾すると、Cが契約上の買主となり、所有権は直接AからCに移転します。
この場合も、登記簿上はAからCへの移転となりますが、契約書上は「A–B売買契約」「B–C地位譲渡契約」「Aの承諾」という三つの書面構成が必要です。地位譲渡料などの経済条件も、契約の中で明確に定めます。
第三者のためにする契約で求められる条項
第1の契約(A–B間)に盛り込むべきポイント
第三者のためにする契約方式を採る場合、A–B間の売買契約には次のような条項が求められます。
- 本契約は第三者Cの利益のために締結すること
- 所有権移転先をCとし、Bは所有権を取得しないこと
- Cが受益の意思表示を行うことを前提とすること
- Cの受益の意思表示がなされたときに、AからCへ所有権が移転すること
これらの条項により、契約の実体が「AからCへの直接移転」であることが明確になり、登記原因証明情報とも整合します。中間者Bが登記上現れないという結果だけを見るのではなく、実体としてもBが所有権を取得しない構造であるかどうかが重要です。
第2の契約(B–C間)の位置づけ
第三者のためにする契約方式では、B–C間の契約は、Cがどの条件で受益するかを定める契約として位置づけられます。宅建業法の観点からは、B–C間を他人物売買の形式で締結しつつ、前述の施行規則の適用除外により運用するケースもあります。
いずれの場合も、最終的な所有権取得者はCであること、Cがどのタイミングでどのような権利義務を負うかが契約書上明確であることが重要です。あいまいな書きぶりは、登記実務の段階で不明点を生みやすくなります。
買主の地位の譲渡で求められる条項
A–B売買契約に必要な合意事項
買主の地位の譲渡方式では、まずA–B間の売買契約において、買主地位の譲渡を前提とする合意を入れておくことが望まれます。代表的なポイントは次のとおりです。
- Bが本契約上の買主としての地位を第三者Cに譲渡できる旨
- その譲渡にはAの承諾を要する旨
- 譲渡が行われた場合、以後の代金支払義務やリスク負担をCが承継する旨
これにより、後にBからCへの地位譲渡が行われた際、A・B・Cの三者間で権利義務関係が明確になります。
B–C地位譲渡契約とAの承諾書
次のステップとして、BとCの間で「買主の地位の譲渡契約」を締結します。この契約では、
- BがA–B売買契約における買主としての地位をCに譲渡すること
- Cがその地位とともに、未払代金支払義務などの契約上の義務も承継すること
- 必要に応じて、譲渡対価(地位譲渡料)や支払条件を定めること
を明文化します。あわせて、Aがこの譲渡を承諾したことを示す承諾書を作成し、登記原因証明情報とも整合させます。こうした書面構成により、所有権がAからCへ直接移転する実体が裏付けられます。
新・中間省略登記の実務上の問題点
宅建業法上の消費者保護とのバランス
新・中間省略登記は、取引コストの削減と不動産流通の円滑化に寄与しますが、消費者保護の観点からの課題もあります。とくに買主の地位の譲渡方式や、無名契約を用いた構成では、B–C間の契約が宅建業法上の典型的な「売買契約」とは異なる扱いになる場合があります。
その場合、重要事項説明義務や瑕疵担保に関する特例など、宅建業法が用意している保護が及びにくくなります。国土交通省の通知でも、こうした契約形式を採用する際には、買主が自らの法的地位や保護の範囲を十分理解したうえで契約することが前提とされており、業者側には丁寧な説明が求められています。
法務局実務と事前照会の重要性
新・中間省略登記の枠組みは国レベルで整理されていますが、具体的な登記申請の可否は、登記原因証明情報や契約書の内容に基づき、各法務局が判断します。そのため、同じようなスキームでも、書面の作り方や説明の仕方によっては追加の確認が入る場合があります。
実務では、司法書士が事前に法務局と照会し、求められる書類や記載内容をすり合わせておくことが多くなりました。オーナーや管理会社の立場からは、新・中間省略登記を希望する場合、必ず専門家に早い段階から相談し、スキームと契約内容を詰めていくことが重要です。
まとめ
従来の中間省略登記は、登記簿の公示機能を損ない、権利関係の透明性を低下させることから、不動産登記法および登記原因証明情報の制度の下で原則禁止となりました。一方で、不動産市場のニーズに応える形で、「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲渡」という二つの契約類型に限り、実体としてAからCへ直接所有権が移転する場合の登記が整理されました。
新・中間省略登記は、単なる登記手続の省略ではなく、契約構成と実体に裏付けられた「直接移転登記」です。スキームを採用する際には、契約条項の設計、登記原因証明情報との整合性、宅建業法上の消費者保護、そして法務局との事前調整が欠かせません。
賃貸オーナーや不動産管理会社としては、「中間省略」という言葉だけにとらわれず、取引の実体をどう設計し、どのように登記で反映させるのかを意識することが重要です。新・中間省略登記を検討する場面では、早い段階から司法書士や弁護士と連携し、安全で透明性の高いスキームを選択することが、結果的にトラブルを防ぎ、不動産経営の安定につながります。
用語紹介
- 買主の地位の譲渡
- 売買契約における買主としての地位(権利と義務)を、元の買主から第三者に移転することを指します。
- 登記原因証明情報
- 所有権移転などの登記申請時に、その原因となる契約内容や日付を証明するために提供する情報を指します。
- 他人物売買
- 売主が所有権を持たない不動産について、将来の取得などを前提に買主と売買契約を結ぶことを指します。