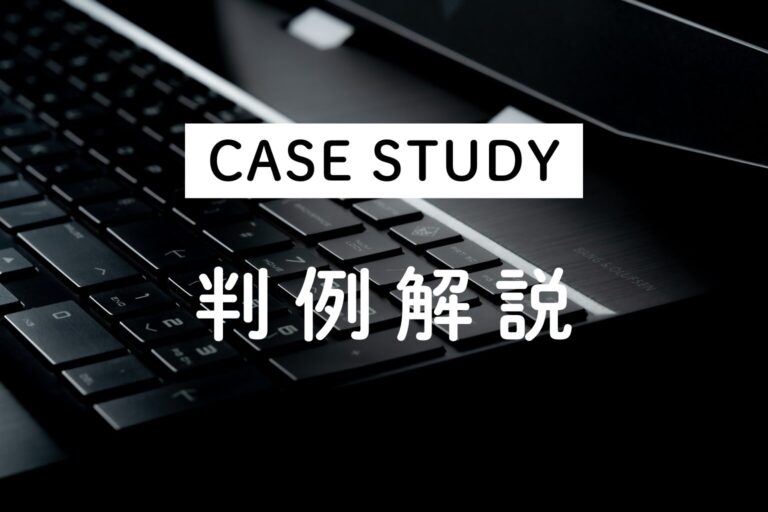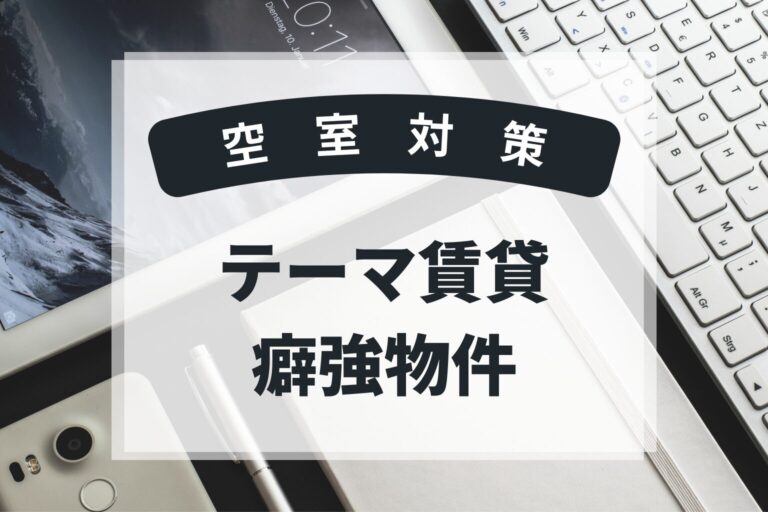はじめに
賃貸アパート・マンションを新築・管理する際には、建築基準法や都市計画法だけでなく、消防法や各自治体の条例も踏まえて計画する必要があります。特に、共同住宅における消火器の設置義務や設置本数、点検や交換のタイミングは、入居者の安全とトラブル防止の観点から避けて通れません。
本記事では、消防法令の考え方を前提に、共同住宅の消火器設置義務の基本、能力単位と所要能力単位の関係、耐用年数や点検・交換の実務、共用部での劣化対策、そして処分方法までを、賃貸オーナー・管理会社向けに整理します。
消火器の設置義務と免除条件
共同住宅における消火器の設置義務は、消防法・消防法施行令・施行規則に基づいて判断されます。ここでは、法令上の基本的な考え方を整理したうえで、「設置義務が生じるケース」と「免除または軽減される可能性があるケース」を分けて解説します。
法令上の基本的な考え方
消防法施行令別表および関連規定では、建物の用途・延べ面積・階数などに応じて、消火器を含む消防用設備の設置義務が定められています。共同住宅(アパート・マンション)については、延べ面積が一定以上になると消防用設備の設置が必要となり、その一つとして消火器の設置義務が生じます。
一般的な共同住宅の場合、原則として延べ面積が150㎡以上になると、消火器の設置義務が生じるのが目安です。
また、地階・無窓階・3階以上の階で一定面積を超える部分には、延べ面積が小さくても消火器設置義務が個別に発生する特別な規定があり、3階建て以上の物件ではこの点に注意が必要です。
消火器の設置が必要となる主なケース
共同住宅で消火器の設置が必要となる代表的なケースは次のとおりです。
- 共同住宅全体の延べ面積が一定規模以上となり、消防用設備の設置が義務付けられる場合
- 地階・無窓階・3階以上の階で、各階の床面積がおおむね50㎡以上となる場合
- 同一建物内に店舗・事務所などの住居以外の用途が併設されている場合
- 共用廊下が長く、避難経路に死角が多い構造の場合
- 木造・軽量鉄骨造などで耐火性能が十分でない場合
これらに該当する建物では、原則として各階に1本以上、共用廊下が長い場合は2本以上の設置が求められることが一般的です。具体的な本数は、到達距離の基準(目安として20m以内)や建物形状を踏まえ、所轄消防署の指導に従う必要があります。
免除・軽減される可能性があるケース
一定の構造・延べ面積・避難経路等の条件を満たす共同住宅では、条例や特例基準により消火器設置が免除または軽減される場合があります。
- 地上2階建て程度までの比較的小規模な共同住宅
- 延べ面積が小さく、避難に支障が少ないと判断される構造
- 開放型廊下など、煙が滞留しにくい構造
- 他の消防用設備との組み合わせで安全性が確保されている場合
ただし、免除や軽減の可否は所轄消防署の判断によります。延べ面積のみで一律に判断せず、必ず個別に確認してください。
最終的な設置義務や本数は、建物の構造や用途、避難経路、他の消防用設備との関係を踏まえて、所轄消防署が判断します。
能力単位と所要能力単位の考え方
消火器の性能や、建物側で必要となる消火能力を理解しておくと、設置本数の考え方が整理しやすくなります。
能力単位(消火器側の性能)
消火器に表示される「10A-3B-C」などの表記は、対応できる火災の種類と性能を示します。AやBの前に付く数字は、模型火災試験による性能指標であり、床面積を直接示すものではありません。
所要能力単位(建物側の必要量)
建物側で必要とされる消火能力は「所要能力単位」として定められています。
- 非耐火構造:延べ面積おおむね100㎡ごとに1単位
- 耐火構造:延べ面積おおむね200㎡ごとに1単位
計算はあくまで目安であり、詳細は消防設備業者や消防署への確認が前提です。
耐用年数・点検・交換サイクル
耐用年数の目安
- 業務用消火器:製造からおおむね10年
- 住宅用消火器:おおむね5年
※注意:共同住宅の共用部で法令義務として設置する場合は、必ず業務用消火器を使用してください。住宅用消火器は義務設置の本数に含まれません。
点検と報告の義務
- 機器点検:6か月ごと
- 消防署への報告:原則3年に1回(複合用途の場合は1年に1回となることがあります)
処分の注意点(リサイクル)
消火器は一般ゴミとして廃棄できません。交換後の消火器は、消火器リサイクルシステムに基づき、指定窓口への持ち込みや回収依頼が必要です。
共用部での劣化対策
共用部に設置する消火器は、劣化を防ぎ、誰でもすぐ使える状態を保つことが重要です。
消火器ボックス・固定器具の活用
ボックス収納や壁面固定により、紫外線・湿気・転倒による破損を防げます。
標識による視認性の確保
蓄光標識などを設置し、停電時でも位置が分かるようにしておくと初期消火につながります。
まとめ
共同住宅の消火器設置義務は、延べ面積150㎡以上を一つの目安としつつ、階数や構造、用途によって判断されます。共用部では業務用消火器を設置し、点検・交換・処分まで含めた管理が欠かせません。
最終判断は所轄消防署の指導に従うことが前提ですが、本記事の内容を押さえておくことで、設計や管理の検討をスムーズに進められます。
用語紹介
- 能力単位
- 消火器が消火できる火災規模を示す性能指標です。
- 所要能力単位
- 建物側で必要とされる消火器能力の計算基準です。
- 業務用消火器
- 法令に基づく設置義務の対象となる消火器です。
- リサイクルシール
- 廃消火器を適正処理するための仕組みです。