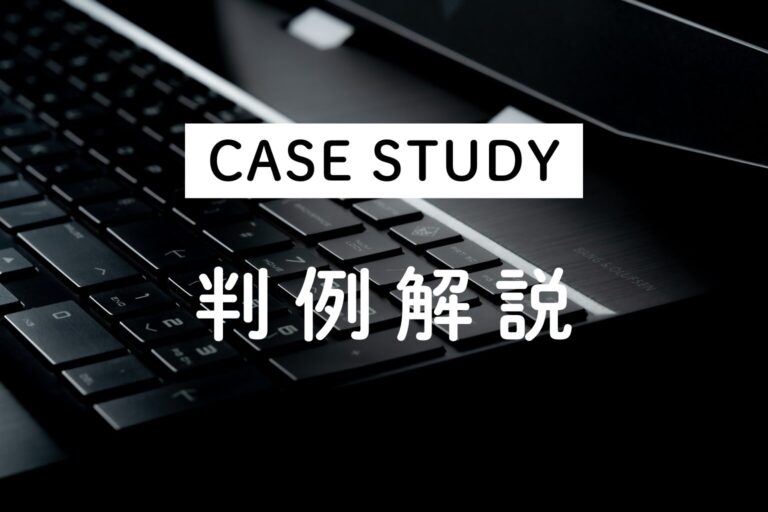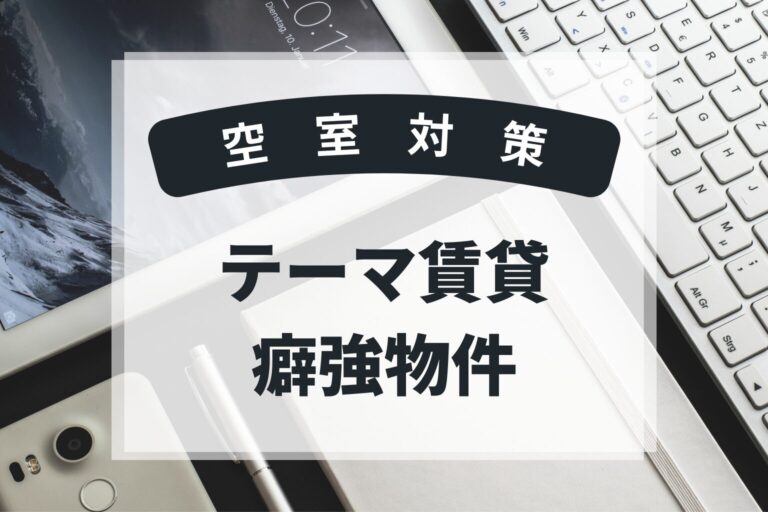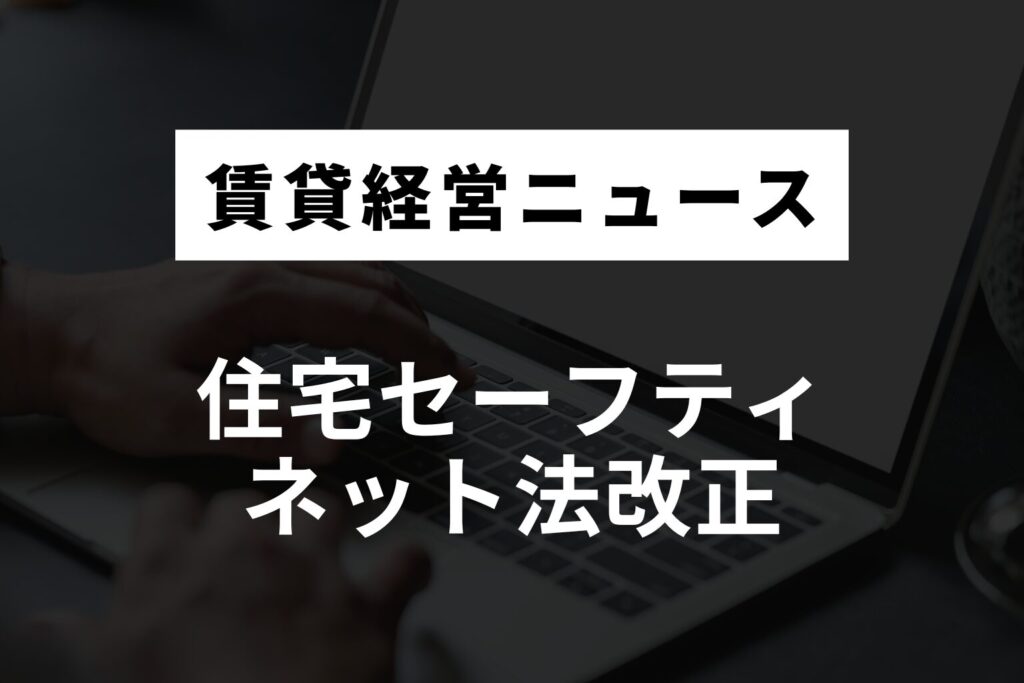
はじめに
2025年10月から施行される「住宅セーフティネット法」の改正は、初めて賃貸管理に取り組むオーナーや自主管理オーナーにとって大きな転換点となります。これまで高齢者や単身世帯など、入居が難しい層を受け入れる際には「滞納」「孤独死」「残置物処理」などのリスクがあり、多くのオーナーが二の足を踏んできました。
今回の改正では、こうした課題に対して国や自治体が制度を整え、保証・残置物処理・見守りサービスなどを支援する仕組みが強化されます。オーナーにとってはリスクを抑えながら空室を埋め、入居率を高めるチャンスでもあります。
さらに、行政や居住支援法人の連携が強まることで、これまで民間が単独で抱えていた負担の一部が公的支援に移行することも期待されています。制度を正しく理解し準備を整えることが、長期的な収益改善や物件価値向上につながります。
改正の背景と目的
少子高齢化や単身世帯の増加は年々進み、住まい確保に配慮を要する人々が増えています。民間賃貸住宅が主要な受け皿となる一方で、オーナー側は「家賃滞納」「孤独死」「残置物処理費用」などのリスクを負い、入居拒否が社会問題化していました。
こうした背景を受けて2017年に「住宅セーフティネット法」が施行され、2025年に大幅改正が予定されています。改正の目的は、要配慮者が安心して入居できる環境をつくるだけでなく、オーナーに対しても補助・保証などの制度を整え、貸しやすい環境を作ることです。
これにより民間賃貸住宅の空室活用が進み、社会全体の住環境改善につながることが期待されています。地方都市や郊外の築古住宅の活用、地域コミュニティの維持、空き家対策など副次的効果も見込まれ、オーナーにとっては「物件活用の新しい選択肢」となります。
主な改正ポイント
改正の柱は大きく5つあります。それぞれオーナーにどんなメリット・注意点があるかを説明します。制度概要だけでなく、現場での運用イメージを理解しておくことが、今後のトラブル防止や補助金活用の成功のカギになります。
終身建物賃貸借制度の導入
入居者の死亡で契約が終了する「終身建物賃貸借契約」が導入され、相続人への権利承継を防ぎやすくなります。契約終了手続きがスムーズになり、トラブル回避につながります。遺族対応や残置物整理に悩んできたオーナーにとって、制度的な後ろ盾になります。
残置物処理の制度化・支援
入居者死亡後や退去後に残置物が大量に残ることはオーナーの悩みの種でしたが、今後は居住支援法人が処理を受託できるようになり、負担軽減が期待されます。自治体と連携することで費用補助を受けられる場合もあり、早めに地域の仕組みを調べておくと有利です。委託範囲・費用・写真記録などの条件を明確化し契約書にも反映させましょう。
家賃債務保証制度の拡充
要配慮者向けに国が認定する保証業者制度が整備され、滞納リスクを保証でカバーしやすくなります。既存の保証会社との違いや補償範囲を確認し、利用条件を把握しておくことがポイントです。連帯保証に頼らない与信設計を取り入れることで、審査ハードルを下げつつオーナー側の安心を確保できます。
居住サポート住宅・見守りサービス
新設される「居住サポート住宅」では、見守り・安否確認・福祉サービスの提供など、入居中の支援が制度として位置付けられます。機器導入(センサー・通報装置等)と運用(対応時間・通報先・費用負担)の役割分担を整理し、入居者への説明資料と同意取得のプロセスを整備しておくと、運用開始後のトラブルを抑えられます。
補助金・助成制度の拡充
改修補助・家賃低廉化・保証料補助など、オーナーの経済的負担を軽くする支援策が拡大されます。自治体ごとにメニューや申請時期が異なるため、年間計画に申請スケジュールを組み込み、見積・仕様書・写真・台帳などのエビデンス整備を習慣化しましょう。
オーナーがすべき準備と対策
- 登録住宅制度の検討:対象物件の要件(面積・設備・管理体制など)を洗い出し、候補物件の優先順位を決めます。登録することで補助金・税制優遇などのメリットが得られる場合があります。
- 物件改修・設備更新:バリアフリー化(段差解消、手すり、照度アップ)、見守り機器の導入計画を立案。工期と募集計画を連動させ、空室期間を最小化します。
- 契約書条項の見直し:終身建物賃貸借の終了事由、敷金精算、残置物の扱い、原状回復の範囲を明文化。重要事項説明での告知ポイントもチェックリスト化しておきましょう。
- 保証会社との連携:認定保証業者の商品設計を比較検討し、滞納発生時の連絡フロー・回収プロセスを社内共有します。
- 居住支援法人との協力体制:残置物処理、見守り、相談対応の分担・費用・連絡チャネルを事前合意。緊急時の鍵管理・立会い基準も取り決めておくと安心です。
- 維持管理・定期点検:登録後の要件維持に向け、年次計画(共用部点検、設備更新、消防・ガス・電気の保守)と記録の保管方法を整備します。
注意すべきリスク・留意点
コストと採算性:改修・機器導入・運用費用を補助金で相殺しきれない場合もあります。賃料改定や入居率向上の効果を見込み、投資回収期間(ROI)を試算して意思決定しましょう。
業務の複雑化:見守り・通報対応・連携機関連絡など、業務プロセスが増加します。社内マニュアルと担当割、外部連携のSLA(応答時間・報告様式)を定義して、属人化を防ぎます。
制度要件の適合と継続:対象条件の誤解や、登録後の要件未充足はリスクです。定期点検と記録保管を徹底し、制度変更時は契約・説明書類も即時アップデートしましょう。
入居者コミュニケーション:終身建物賃貸借の趣旨や残置物の扱いは誤解を招きやすい領域です。募集段階で図解やQ&Aを用意し、トラブルを未然に防止します。さらに、制度活用に伴う事務負担や書類管理の手間も無視できません。事務作業を外部委託する、管理ソフトを導入するなど、効率化策を検討しておくことも長期的にはプラスになります。
まとめ
2025年の住宅セーフティネット法改正は、賃貸経営オーナーにとってリスク軽減と物件活用拡大のチャンスです。制度を義務として受け止めるのではなく、物件価値の向上・入居率アップの機会と捉え、早めに準備を進めることが長期的に安定した賃貸経営につながります。
賃貸経営PLUSでは、こうした制度改正の最新情報や実務ノウハウを随時更新し、初めて賃貸管理を始める方・自主管理で奮闘するオーナー様をサポートしていきます。将来的には補助金情報や契約書雛形の提供、支援法人リストの公開など、さらに実務に役立つコンテンツを充実させていく予定です。
-768x512.jpg)