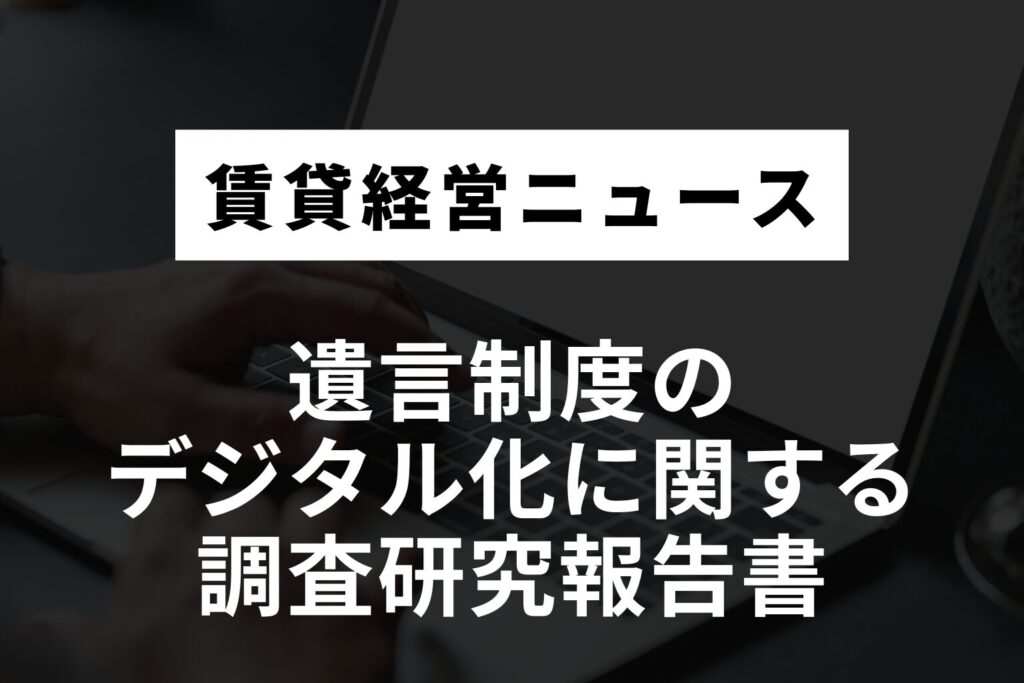
はじめに
第1回では、日本の遺言制度の全体像と、賃貸オーナーにとって遺言が経営判断の一部であることを整理しました。
今回は、その中でも最も身近で利用されることの多い「自筆証書遺言」について詳しく解説します。
自筆証書遺言は、費用をかけずに自分の意思を形にできる制度です。
一方で、制度の理解が不十分なまま作成すると、相続発生後にトラブルを招くケースも少なくありません。
本記事では、賃貸不動産を所有するオーナーの視点から、自筆証書遺言の基本ルール、実務上の注意点、失敗しやすい具体例までを整理します。
「書いたつもりの遺言」が無効にならないために、ぜひ最後まで確認してください。
自筆証書遺言とはどのような制度か
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きして作成する遺言の方式です。
民法で定められた要件を満たせば、公証人や証人を立てることなく作成できます。
最大の特徴は、思い立ったときにすぐ作成できる点と、原則として費用がかからない点です。
「まずは簡単に意思を残したい」と考える賃貸オーナーにとって、心理的なハードルが低い制度と言えます。
しかし、自筆証書遺言は形式面の要件が厳格です。
内容がどれだけ合理的であっても、形式を欠けば無効と判断される可能性があります。
この点が、実務上の最大の注意点です。
自筆証書遺言の成立要件と注意点
自筆証書遺言が有効と認められるためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。
初級者の方は、まず次の三点を確実に押さえておくことが重要です。
(1)遺言者本人が全文を自書すること
遺言書の本文は、遺言者本人が自分の手で書く必要があります。
パソコンで作成した文章や、第三者が代筆したものは原則として認められません。
文字の上手さは問題になりませんが、誰が見ても本人の意思と分かる内容であることが求められます。
(2)作成日付を明確に記載すること
作成日付は、「令和〇年〇月〇日」のように、特定できる形で記載する必要があります。
年月のみの記載や、日付が判別できない表現は無効となる可能性があります。
複数の遺言書が見つかった場合、日付が新しいものが優先されるため、この点は特に重要です。
(3)署名と押印を行うこと
遺言書の末尾には、遺言者本人の署名と押印が必要です。
署名がない場合や、本人の意思が確認できない場合には、遺言として成立しません。
財産目録に関する特例(2019年法改正)
以前は、自筆証書遺言では財産目録も含めてすべてを手書きする必要がありました。
しかし、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳・登記簿謄本のコピーを添付することが認められています。
これにより、賃貸不動産や複数の金融資産を所有するオーナーでも、比較的負担を抑えて遺言を作成できるようになりました。
ただし、添付する財産目録の各ページには、遺言者本人の署名と押印が必要です。
実務で起こりやすいトラブルと失敗例
自筆証書遺言で特に多いのが、内容の曖昧さを巡るトラブルです。
賃貸不動産を含む場合、この点はより深刻になりがちです。
例えば、「〇〇市にあるアパートを長男に相続させる」といった表現は、一見問題がないように見えます。
しかし、同一市内に複数の物件を所有している場合や、相続人の解釈が分かれた場合には、争いの原因になります。
実務上は、不動産の表示を登記簿謄本どおりに記載することが重要です。
「〇〇市〇丁目〇番〇の土地および建物」といった形で、客観的に特定できる表現を用いる必要があります。
また、自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。
検認とは、遺言書の存在と内容を確認するための手続であり、相続手続を進める前段階として位置づけられています。
検認が終わるまで、売却や名義変更といった実務が進められない場合もあります。
賃貸経営に与える影響を考えると、この点は事前に理解しておく必要があります。
法務局の遺言書保管制度をどう考えるか
自筆証書遺言の弱点を補う制度として、法務局による遺言書保管制度があります。
この制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で安全に保管してもらうことができます。
保管制度の主なメリット
最大のメリットは、遺言書の紛失や改ざんのリスクが大幅に低下する点です。
また、保管制度を利用した遺言書については、相続開始後の検認手続が不要となります。
さらに、相続人に対して遺言書の存在が通知される仕組みがあるため、「遺言書が見つからない」という事態を防ぐことができます。
注意すべき点とデメリット
一方で、保管制度を利用するためには、数千円程度の手数料がかかります。
また、法務局での事前予約や本人確認書類の持参など、一定の手続きが必要です。
遺言書の用紙サイズや余白など、法務局が定める様式ルールを守る必要がある点にも注意が必要です。
すべてのケースで最適とは限らないため、自身の状況に応じて利用を検討することが重要です。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式不備や実務上のリスクを伴う制度です。
特に賃貸不動産を所有している場合、その影響は相続発生後に顕在化しやすくなります。
成立要件を正しく理解し、財産目録の特例や保管制度を適切に活用することで、
自筆証書遺言の弱点を補うことができます。
次回は、公正証書遺言について、なぜ実務上の安全性が高いとされているのかを詳しく解説します。
自筆証書遺言との違いを比較しながら、最適な選択肢を考えていきましょう。
用語紹介
- 自筆証書遺言
- 遺言者本人が全文を手書きして作成する遺言の方式です。
- 検認
- 家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続を指します。
- 法務局の遺言書保管制度
- 自筆証書遺言を法務局で保管し、紛失や改ざんを防ぐ制度です。



