
賃料滞納を理由に貸主が入居者不在中に無断で鍵を交換し、立入を制限した事案です。本件では、貸主による自力救済行為の適法性が争点となり、裁判所は「自力救済は原則として許されない」との立場を明確にしました。貸主・管理会社の現場対応に直結する重要な判例です。
事案の概要
本件は、賃料滞納が続いた借主に対し、貸主が法的手続を経ずに室内へ立ち入り、鍵を交換して入居者の入室を妨げたことから、借主が損害賠償を請求した事案です。
貸主は「度重なる滞納と連絡不通により、契約が実質的に終了した」と主張しましたが、借主は「契約解除通知も受けておらず、居住権を奪われた」と反論しました。
判決の要旨
- 自力救済の原則禁止:民事上の紛争解決は、法的手続によることが原則であり、貸主が自己判断で占有を奪回する行為は違法である。
- 貸主の行為の評価:借主に対する解除通知・明渡訴訟を経ずに鍵を交換し、入室を妨げた行為は、居住権の侵害にあたると判断。
- 警察立会いの有無:警察官が同席していても、民事上の権限を補うものではないため、違法性が消滅することはない。
- 損害賠償の範囲:裁判所は、入居不能期間中の賃料相当額および慰謝料の一部を認容した。
位置づけと実務上のポイント
1. 「自力救済禁止」の原則確認
本判決は、賃貸物件における占有回復・鍵交換行為が原則として違法であることを改めて確認したものです。民法上、貸主であっても契約関係が継続中である限り、入居者の占有を一方的に奪うことはできません。
2. 管理会社・貸主が取るべき対応
- 滞納や連絡不通の場合でも、法的な明渡訴訟や解除通知を経ること。
- 現地確認・室内確認は、必ず同意または執行官の立会いを得て行う。
- 警察立会いは刑事トラブル防止には有効だが、民事的な正当化にはならない。
3. 借主保護と信頼関係
借主が占有を維持している段階では、たとえ滞納があっても、契約上の地位が残っています。信頼関係が破壊されたとしても、解除・訴訟という正規の手続きを経ない限り、貸主は実力で排除できません。
まとめ
東京地判平成30年6月12日判決は、鍵交換・室内立入といった自力救済行為の違法性を明確に判断した事案です。貸主・管理会社は、法的手続きを経ずに入居者の占有を奪うことのリスクを十分に認識する必要があります。現場対応時には、弁護士や専門機関と連携し、手続的に安全な明渡しを進めることが求められます。
用語紹介
- 自力救済
- 裁判手続きを経ずに、当事者が自らの権利を実力で実現しようとする行為。原則として違法とされる。
- 占有
- 物を事実上支配している状態。借主が建物に居住している場合、その建物について占有権を有する。
- 信頼関係の破壊
- 貸主・借主間の関係が回復不能なほど損なわれ、契約の継続が困難な状態。解除事由となる場合がある。
- 明渡訴訟
- 借主に対し、建物の占有を明け渡すよう求める訴訟手続。法的手続を経て初めて強制執行が可能になる。
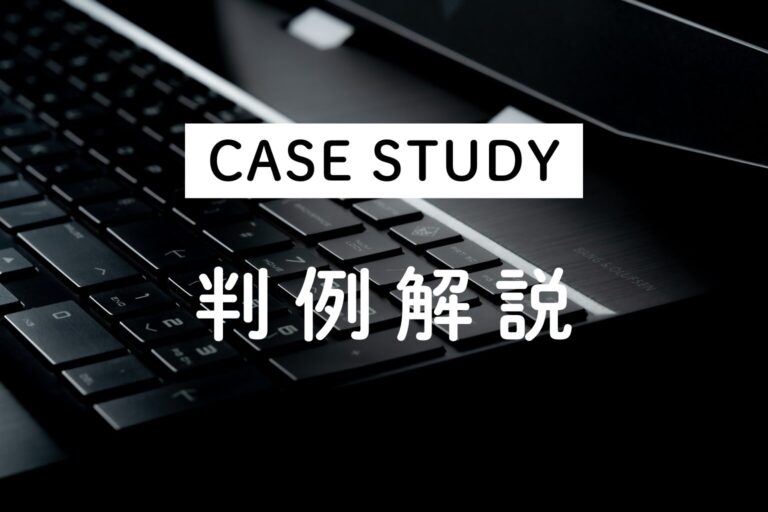
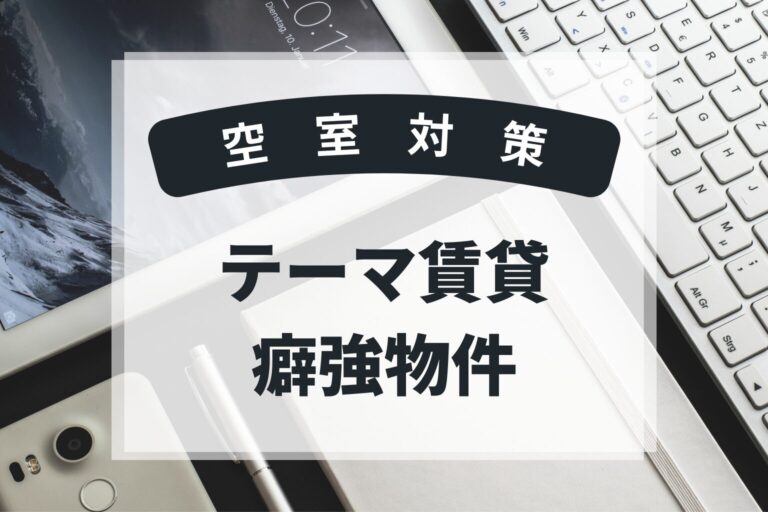
1 “【判例解説】無断鍵交換と自力救済の可否(東京地判 平成30年6月12日)”で考えました
コメントは閉じられています。